新しい定款について検討を要する事項(その1)
こんにちは!
いずみ会計事務所の税理士の浦田です。
公益法人の法律が変わりましたので、団体が成り立つ基礎となる定款も見直す必要があります。
従来、財団法人では寄付行為と呼ばれていたものが、今後「定款」という名称で統一されます。
具体的にどのような項目を見直す必要があるのか、確認してみたいと思います!!
■定款変更をするか、それとも現状のままとするかの選択を必要とする事項
●社員による総会開催召集権の議決権の割合
社団・財団法人法第37条に
社員による総会召集をする際に当該社員が必要とする議決権の割合が
「10分の1(5分の1以下の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)」
と規定され、その割合の検討が必要になります。
今までの定款でこの割合を個別にアレンジ(変更)されていた団体もあるようです。
今一度、見直ししてみましょう。
●総会召集の通知期間
社団・財団法人法第39条に
「社員総会の1週間前までに通知」
と規定されています。
通知期間の検討をしなくてはなりません。
事務局は準備の時間も必要ですが、総会等に出席いただかないことには
何事も決まりませんから、事前に通知をすることも大事ですよね!
●社員提案権の議決権の割合
一般社団・財団法人法第43条第2項に
社員提案権を
「議決権の30分1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合)」
と規定されています。
その割合の検討が必要です。
ここも従来の定款では上記と異なる内容でアレンジ(変更)されている団体もあります。
注意して見直ししましょう。
●理事会、監事又は会計監査人の配置
社団・財団法人法第60条第2項に
「定款の定めによって理事会、監事又は会計監査人を置くことができる」
と規定されています。
今後も理事会を設置するかの判断をしなくてはなりません。
やはり、理事会は団体の機関として重要な会議体制であると私は認識しています。
●監事の任期
社団・財団法人法第67条に
監事の任期に関し
「選任後4年。ただし、定款又は社員総会の決議によって選任後2年以内」
と規定されています。
監事の任期の検討が必要です。
一度、就任お願いしたら、おおむね上記の期間は役割を担っていただく必要があります。
人事の人選は難しいですが、大事ですよね!
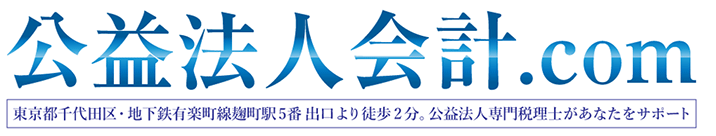
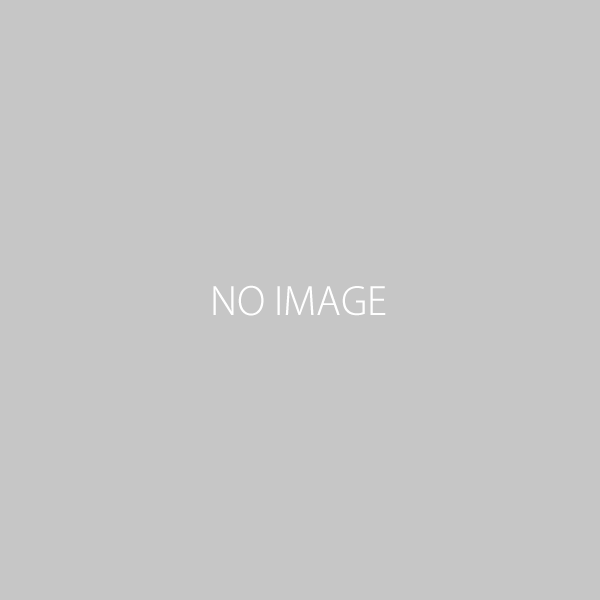
この記事へのコメントはありません。